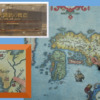【第80回】「少子化(Declining Birthrate)」の真因と帰趨/在留外国人と科学技術への依存是非《4/4》―人工知能(AI)依存の功罪と限界 ―

⇧フランスの彫刻家 Auguste Rodin の代表作『考える人(Le Penseur)』塑像(「京都国立博物館」前庭展示)と、作品に対峙する Wolf(脳神経学博士・当社海外渉外顧問)
「国立西洋美術館(独立行政法人 国立美術館)」 考える人(拡大作)|国立西洋美術館 によれば、Auguste Rodin は『考える人』について次の様に述べている。「扉の前でダンテが岩の上に腰を下ろし、詩想に耽っている。彼の背後には、ウゴリーノ、フランチェスカ、パオロなど『神曲』のすべての人物たち。この計画は実現されなかった。全体から切り離された痩身の苦悶するダンテの姿は、意味がなかった。私は最初のインスピレーションに従って別の思索する人物を考えた。裸の男で岩の上に坐り、両足を引き寄せ拳を歯にあてて、彼は夢想している。実り豊かな思索が彼の頭脳の中でゆっくりと確かなものになってゆく。彼はもはや夢想家ではない。彼は創造者である」。
『考える人』の塑像は、「京都国立博物館(独立行政法人 国立文化財機構)」「国立西洋美術館」をはじめ日本に5体、世界で21体が存在する。
※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。
日本社会で「出生数」(Number of Births)の減少とこれによる「人口」(日本人人口)の減少局面に歯止めがかからない。「少子化」(Declining Birthrate)対策は國體護持の要諦であり、我が国の経済成長(労働力確保・消費拡大)や社会保障・公共サービス(医療・高齢者介護・年金・教育など)の維持にとり喫緊の課題である。とりわけ世界で最も高い「高齢化率」の我が国で高齢者の支え手が減少し、介護の負担が増す現状にある。本稿では、大東亜戦争(対米戦争)直後のベビーブーム期の社会状況に着目。これとの対比で「家」と「国家」重視の価値観を軸に、近年長期化している「少子化」の原因と真因を考察する。
また今後の「労働力人口」(Labor Force Population/就業者と完全失業者の合計)や「生産年齢人口」(Working Age Population/15~64歳)、とりわけ「35歳以下の若年層」の減少がもたらす帰趨について捉える。すなわち「在留外国人」(Foreign Resident)と「科学技術」(Technology)への労働依存の実態である。時宜を得た Technology として、「人工知能(AI:Artificial Intelligence)」「人型ロボット(Humanoid Robot)」「無人機(Drone)」がある。なお労働力人口は現状、漸増傾向にあり、この要因には女性と「高齢者」(65歳以上)の労働参加がある。
昨年あたりから朝新聞を開けば政治・経済から社会面まで、あまねく「AI」の二文字を見ない日はない。メディアがその便益を過熱気味に煽る人工知能(AI)の喧騒は食傷気味である。AI の利用・導入により、大幅な生産性向上や少子化による生産年齢人口の減少に伴う労働力の補完が期待されている。また AI 銘柄が今夏以降の株価最高値の更新を牽引しているのは事実だ。しかしその一方、AI への過度の依存により社会に生じる問題点として以下の項目が挙げられる。
・人間の思考能力の低下、思考主体の放棄(論理的判断力・問題解決力・創造力等)
・人間性の喪失、放棄(尊厳や倫理の毀損)
・人間関係の希薄化、社会の閉塞感(家族や他者との対話・交流の減少)
・労働市場への影響(自動化技術による特定職種における代替・雇用の縮小)
・AI の悪用(不正目的で使用されるリスク)
・著作権上の扱い(著作物性・権利の帰属・既存著作物の権利侵害等)
・事故発生時の責任の所在(AI を搭載した自動運転車や人型ロボット、Drone 等)
・生成過程のブラックボックス化(複雑なアルゴリズムに基づく動作)
・開発運用コスト(専門人材の確保、半導体開発競争、電力消費の増大)
・制御の難しさ(AI の予期せぬ行動・暴走に対する安全性)
・誤情報や非現実的情報の生成(社会に与える信頼性の損失、混乱の助長)
・偏見や先入観(Bias)の学習(性別・人種・宗教等)
・非倫理的な判断や回答(倫理的学習データの不足)
・プライバシーやセキュリティの侵害(個人情報や機密情報に係る大量データを収集)
東京大学名誉教授で工学博士の西垣通(にしがきとおる)氏は、著書『』の「はじめに」で次の様に述べている(引用・注釈・下線筆者)。『とりわけ私の神経に突き刺さっているのは、デジタル技術の白眉として賞賛されているインターネットと AI (人工知能)の、ここ二、三十年の発達普及という出来事なのだ。なぜならそれは、下手をすると、科学技術の暴走を防ぎうまく活用するための人間の判断力そのものを、致命的に麻痺させる魔力を持っているからである。にもかかわらず、目先の利益追求に狂奔するエリートたちは、決してそういう危険を直視しようとしない。』さらに『古来、ユダヤ=キリスト教と仏教とでは、自然というもののとらえ方が全く異なっていた。科学は自然を対象にするのだから、そこで文化的に亀裂が露呈するのは当然である。こうして例えば、AI や脳科学のアプローチがはたして「心の解明」さらには「心の製造」にまでつながるかどうか、といった汎用知(※1)をめぐる問いが具体的に顕在化してくる。デジタル社会で蔓延するのは心の病だから、この種の難問を放置することはできない。』と。筆者は首肯する。
また同氏は、上記に先立つ著書『』の「第5章 AI の論理と誘惑」で述べている(引用・注釈・下線筆者)。『トランス・ヒューマニスト(※2)たちの主張は、ユダヤ=キリスト一神教の伝統をもたないわれわれ日本人には同調しにくいところがある。生きているわけでもない物質のなかに超越的な知性が宿り、それに人間が奴隷のように従うという未来図は、SF オタクでもなければ違和感をもつはずだ。とはいえ、短期的な経済成長しか頭にない産官学のリーダーも少なくないし、CPS(Cyber Physical System)だのソサエティ5.0だのといった宣伝文句につられて、彼らがフロリディの情報圏構想(※3)に飛びつく可能性もゼロではない。』「第6章 データ至上主義からの脱出」では『本書で述べてきたように、「意味」とは本来、生きていく文脈/状況のなかに埋め込まれた価値のことである。だからこそ、生き物ではない AI には、記号を論理的に処理できても文脈把握ができず、意味理解が不可能なのだ。要するに、AI 時代に生きるためには、感性をみがき、他者の気持ちを直観できる能力が大事なのである。人生の喜怒哀楽への想像力を欠き、契約書のような実用的文章を形式的に手早く論理処理するだけの、コンピュータのような人間が日本列島にあふれたらどうなるのか。間違いなくそれは、ハラリ(※4)の懸念する陰鬱な未来社会の姿である』と。言い得て妙である。
これに符合し、「一般社団法人 京都哲学研究所」 京都哲学研究所 を創設した NTT 取締役会長の澤田純氏は、著書『パラコンシステント・ワールド―次世代通信 IOWN と描く、生命と IT の〈あいだ〉』の「第Ⅰ部 IOWN ビジョン <あいだ>の思想とテクノロジーへ」で、AI の限界について触れている(引用・下線筆者)。『しかし現状の AI は過去の膨大なデータから学習するため、前提条件をはるかに超えるような想定外のことには役立ちません。また AI は人間のような直感や常識、暗黙知などを持ち合わせていないため、もし、AI に人間のような判断を期待するのであれば、それらをすべてデータとして記述して与える必要がありますが、いまだにその手法は見出されていません。さらに、現状の AI は「意味」を理解しているとは言えそうにありません。翻訳アプリがそれなりに使えるのは、対応する言葉を膨大に集めた辞書を備えているからであって、AI が言葉の意味そのものを理解したうえで翻訳しているわけではないのです。しかも、現在ブームの深層学習を利用する場合、中身の大部分がブラックボックスとなることから、どうやって答えを導き出したのかを詳細に説明できない場面が数多くあります。AI は人工知能と言われながら、ラーン(学習)はできても、シンク(考える)はできないのです。』
【後日追記】日経新聞が第1回京都会議を特集――AIの舟で人間はどこへ 混迷の時代に哲学の灯火 | ニュース・記事一覧 | 京都哲学研究所
(※1)汎用知:「汎用人工知能」(Artificial General Intelligence:AGI)すなわち特定分野に特化せず、人間が実現可能なあらゆる知的作業を人間と同等かそれ以上に理解・学習・実行可能な人工知能
(※2)トランス・ヒューマニスト:超人間主義者(Transhumanist)すなわち、生命を促進する原則と価値に基づき、科学技術により現在の人間の形態や限界を超克した知的生命への進化の継続と加速を追及する生命哲学の一潮流(の信奉者)
(※3)フロリディの情報圏構想:「情報圏」(Infosphere)すなわち、イタリアの情報哲学研究で知られる Luciano Floridi 氏が提唱する、「情報」が中心的な構成要素となりえる情報環境・空間
(※4)ハラリ:Yuval Noah Harari、イスラエルの歴史学者で『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福(Sapiens: A Brief History of Humankind)』『ホモ・デウス テクノロジーとサピエンスの未来(Homo Deus: A Brief History of Tomorrow)』の著者
※参考文献
毎日新聞取材班『世界少子化考 子供が増えれば幸せなのか』、毎日新聞出版、2022年
西垣通『デジタル社会の罠 生成 AI は日本をどう変えるか』、毎日新聞出版、2023年
西垣通『』、NTT 出版、2021年
澤田純『パラコンシステント・ワールド―次世代通信 IOWN と描く、生命と IT の〈あいだ〉』、NTT 出版、2021年
出口康夫『AI 親友論』、徳間書店、2023年