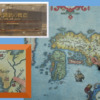【第56回】「作家・政治家」石原慎太郎氏《前篇》―「白」対「有色」/「東京裁判」「GHQ 憲法」に端を発す「戦後80年」/(日独)民族の矜恃―

※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。
「大東亜戦争(対米戦争)後80年」の本年、「芥川賞作家」で国会議員・東京都知事を務めた「保守政治家」石原慎太郎氏の遺した戦後史観、欧米史観(Historical Perspective on the West)を取り上げる。氏は1932年(昭和7年)9月30日、兵庫県神戸市生まれ(その後、北海道小樽市⇒神奈川県逗子市へ転居)の「昭和一桁」「戦後」(仏:Après-Guerre)世代。「昭和」「平成」「令和」を通じ國體の有り様に直言を呈した国士である。位階は正三位。
①東京裁判の真義と靖國神社参拝問題
東京裁判(極東国際軍事裁判/The Tokyo Trial|International Military Tribunal Far East)は、1946年(昭和21年)5月3日~1948年(昭和23年)11月12日において、東京都新宿区市ヶ谷台の陸軍士官学校講堂(現・市ヶ谷記念館)で執行された。これは戦勝国(連合国)が支配者として一方的かつ徹底的に敗戦国を裁き、戦勝国側の「戦争犯罪」(侵略行為や虐殺行為)は完全に免責・不問に付されたものと言われている。米国による広島・長崎への原子爆弾(核兵器)投下はその最たるものであることは自明である。また「平和に対する罪」=「A級」として新しく設けられた戦争犯罪カテゴリーは、従前の国際法に存在しないものであった。にもかかわらず出席した幾多の弁護人による、これは「事後法」であるとの主張はすべて無視され裁判が遂行された。奇しくも市ヶ谷地区は、1970年(昭和45年)の「三島事件」でも因縁の地である。
同氏は、2014年(平成26年)2月12日の「第186回国会 衆議院予算委員会質問」 第186回国会 予算委員会 第6号(平成26年2月12日(水曜日)) において、次の様に述べている。(抜粋、下線・括弧内筆者)
『この裁判というものが、A級戦犯、そういった法的根拠のない罪状を科せられた方たちを裁き、死刑に処し、しかも、その方たちが(靖國神社に)合祀されているということでいろいろな立場の方々から忌避されているということは、私は、これはやはり、この際、国家としてこの問題をはっきりして、それを建前に、総理なら総理の参拝というものを批判する人たちにはっきり物を言ったらよろしいんじゃないかと思う。』
②GHQ 憲法と自主憲法制定の意義
GHQ(※1)司令官 Douglas MacArthurは、戦後占領政策と同時に明治憲法の改正により、日本の長い歴史と伝統ある國體解体を推し進めた。1947年(昭和22年)の現行憲法制定は、明治憲法75条「憲法及び皇室典範は、摂政を置いている間は、変更することができない」の類推違反であるとされる。また戦時国際法・ハーグ陸戦法規第43条「戦勝国が敗戦国を統治するときには、その国の法律に従わなければならない」にも違反している。現行憲法はまさに、GHQ の強い意向により、わずか8日間で、しかも草案を英文で作成されたものである。
【参考】日本国憲法 1947年(昭和22年)5月3日施行 日本国憲法 | e-Gov 法令検索(下線筆者)
(前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(第二章 戦争の放棄)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
石原氏は、2014年(平成26年)10月30日の「第187回国会 衆議院予算委員会質問」 第187回国会 予算委員会 第4号(平成26年10月30日(木曜日)) において、次の様に述べている。(抜粋、下線・括弧内筆者)
『戦勝国アメリカあるいはその他の連合軍にとって、まさにこの漫画(1945年8月19日付「ニューヨーク・タイムズ」掲載(※2))が表示するような、醜悪で非常に危険な存在であった日本を、これから、天皇をいかに扱うかという問題も含めて、いかに統治解体するかということで占領が始まったわけですけれども、その統治解体の有効なすべとして、一方的につくられた憲法が私たちに押しつけられたわけであります。』
氏は GHQ 主導で制定された現行憲法は「無効」であって、「改正」でなく「破棄」の上、自主憲法を制定すべきと主張した。上記の漫画の件(くだり)には続きがあり、晩年の著書『日本よ、完全自立を』で、次の様に述べている。(抜粋、下線・括弧内筆者)
『これはおよそ七十年前に日本とドイツが戦争に敗れ無条件降伏をした直後にアメリカの代表的新聞ともいえるニューヨークタイムズの日本に関する論説に添えられていた漫画です。そして論説の本文には《この醜く危険な化け物は倒れはしたがまだまだ生きている。我々は世界の安全のためにこれから徹底してこの怪物を解体しなくてはならない。》とありました。対照的にドイツの降伏に関しては《この優秀な民族はナチスによって道を誤ったがその反省の上に立ち良き国をつくり直すだろう。われわれはそのために協力しよう》とありました。(中略)時を隔てて戦争に敗れた二つの同盟国に関する論説はきわめて対照的です。』
またドイツが敗戦後示した姿勢について日本に比して述べている。(抜粋、下線・括弧内筆者)
『同盟国として戦いに敗れたドイツは降伏の際連合国に三つの条件をつきつけこれが受け入れられぬ限り徹底して戦うと宣言していた。第一は敗戦の後のドイツの国家の基本法たる憲法はドイツ人自身が作る。第二は戦後の子弟の教育方針はナチズムへの反省をこめてドイツ人自身が決める。第三はいかに数少なくとも国軍はこれを保有する。これに比べて日本は二発の原爆に腰を抜かして全くの無条件で相手の軍門に下ったのだ。』
(※1)GHQ:General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers、連合国軍最高司令官総司令部(事実上の米国単独による日本国占領機関)
(※2)「FOR HIS OWN GOOD」というタイトルの漫画と付属記事、「JAPAN」と付された醜悪な顔、その大きく開けた口内から「MILITARISM」と付された黒い虫歯を、「ALLIED TERMS」と付されたこれまた大きな「やっとこ」で引き抜かんとする図
③欧米諸国による有色民族統治史観
同氏は、日米貿易摩擦の最中であった1989年(平成元年)に『「NO」と言える日本』を著し(共著)大きな話題を呼んだ。その中で、米国が日本に対してもつ人種偏見について言及している。(抜粋、下線・括弧内筆者)
『アメリカ人の人種偏見というのは、自国文化の自負に根を発しているわけで、確かにアメリカ人も含めたホワイトが近代をつくってきた、という自負はわかります。だが、その自負が強烈すぎてアメリカ自身、新興国だから、他国文化、とくにアジアへの視点に曇りがあるのではないか。』
そして同書の題名に関して以下の様に総括している。(抜粋、下線・括弧内筆者)
『「ノー」と言えるカードを持ちながら「ノー」を言わないような失敗は、悔んでも悔み切れない。相手は、感謝などせずに、さらにカサにかかって、あらたな恫喝をしてくるようになってしまう。ヤイター(Clayton Yeutter、Ronald Reagan 政権時の USTR(※3)代表)がはっきり言っていることなんです。日本には圧力をかけるのが一番いい、と。こんなことを言っていると、お前こそ大国アメリカを恫喝しようとして、危なくて仕方ない、などと妙な解釈をひねくり回す日本人がいますが、断わるまでもないことですけれど、屈辱的でない対等な日米関係というものが今こそ必要だから「ノー」と言うべきときには言っておくべきなのです。「ノー」をちらつかせて、バーゲン(bargain/取引)をしなくてはなりません。』
また同氏はその公式ウェブサイト上で、より根底的で長い時間軸における歴史的事実を問うている。それは、大航海時代(15世紀~17世紀)に始まり列強の帝国主義の動き(19世紀)を経て現在に至る、欧米諸国による数世紀に跨る有色民族統治についてである。 歴史の蓋然性について ー白人世界支配は終わったー|コラム|石原慎太郎公式サイト | 宣戦布告.net (抜粋、下線・括弧内筆者)
『つまり中世期以後の歴史の本流はキリスト教圏の白人、つまりヨーロッパの白人による、他のほとんど全ての有色人種の土地への一方的な侵略と植民地化と収奪による白人の繁栄の歴史でした。アフリカや中東、或いは東南アジアの全ての地域は西欧諸国の進出によって国境は区分され植民地化され一方的な隷属を強いられてきたのです。それはまぎれもない事実であり歴史における現実でした。』
『今日声高に人権と民主主義を説いているアメリカもまたあの厖大なアメリカ大陸を、原住民だったアメリカインディアンを殺戮駆逐することで領有し国家として成立したのです。アメリカ大陸の東西を結ぶ大陸横断鉄道は白人たちが一方的に拉致してきて鉄道建設のために働かせた厖大な数のシナ人奴隷によって建設されたのです。』
なお筆者の認識では、この統治側の対象からドイツ(およびドイツ系米国人)を除外したい。ドイツは神聖ローマ帝国の系譜を継ぐ、長い歴史を有する極めて卓越した民族・大国といえる。にもかかわらず、日本同様に領邦国家の権限が強かったため、中央集権体制と統一国家の形成が遅れた(19世紀後半)。そうした歴史の綾から、対外的な(有色人種の土地への)植民地獲得の動きは他の欧米諸国と比して極めて小さかった。また20世紀に入っても、「帝国主義の先発国」対「後発国」の構図となった第一次世界大戦での敗戦に続き、第二次世界大戦の敗戦国として、これまた日本同様に、戦勝国(連合国)から Nuremberg 裁判において、一方的かつ徹底的に裁かれる立場にあった。あたかも出る杭が打たれるが如く、その卓越性故に国力を削がれたのである。剰え(あまつさえ)、米国・英国・フランス・ソビエト連邦の4ヶ国による「分割統治」と、この後生じた Ideology 陣営対立(自由主義社会 × 社会主義社会)の煽りを受け、1989年まで長らく続いた「東西分断」の悲劇を被っている。
氏はまた、「自身と夫人没後の上梓」を託された幻冬舎から2022年(令和4年)刊行の著書『「私」という男の生涯』でも、驕った米国の鼻をくじいた竹下内閣時(運輸大臣)の出来事に触れている。(抜粋、下線・括弧内筆者)
『(前略)いずれにしろ、(東京湾の)辺りは本土近海で本来の(米国)海軍の実弾訓練は領海十二海里外で行われなくてはならぬはずだ。なお近づいて確かめると、その相手はアメリカ海軍の駆逐艦タワーズ号と判明した。彼らは領海の外まで出かけるのが面倒で、領海内でいい加減な見当で大砲の射撃をやってのけたのだった。』
『(前略)私は安易な決着は絶対に認められない、責任者に厳罰を加えて処置するよう、ある人物を介してアメリカの国防総省に申し込まさせた。それによって出てきたのが国防総省の次官補のアーミテージ(Richard Armitage)だった。その彼に私はこの暴挙は首都周辺の多くの民間船舶に危害を及ぼす重大きわまりない違法行為で、それを安易に犯すアメリカ軍全体の信用を損なうもので軽微な懲罰ではすまされないものだと強く言った。するとアーミテージは即座に、「よく分かった。全く馬鹿なことをしたものだ。我々としても呆れている。当然艦長は首にする」と言い切ったものだった。』
(※3)USTR:「米国通商代表部」(The Office of the United States Trade Representative)
※参考文献
石原慎太郎『「私」という男の生涯』、幻冬舎、2022年
石原慎太郎『弟』、幻冬舎、1996年
石原慎太郎『天才』、幻冬舎、2016年
石原慎太郎『日本よ、完全自立を』、文藝春秋、2018年
石原慎太郎『「NO」と言える日本:新日米関係の方策』、光文社、1989年
『三島由紀夫 石原慎太郎 全対話』、中央公論新社、2020年
保阪正康『昭和天皇(上下)』、朝日新聞出版、2019年
石原慎太郎公式ウェブサイト 石原慎太郎公式サイト
大日本帝国憲法(国立国会図書館) 憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生
日本国憲法(国立国会図書館)憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生
石原慎太郎『太陽の季節』(全5編『太陽の季節』『灰色の教室』『処刑の部屋』『ヨットと少年』『黒い水』)、新潮社、1957年