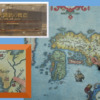【第31回】平成・令和社会への違和感《其ノ一》―母国語教育と Globalism/「言葉の乱れ」が招く國體瓦解(日本語の誤用・外来語の濫用)―

⇧奈良・橿原神宮の紀元祭にて(2025年2月11日 筆者撮影)
※本稿内容は筆者の個人的見解であり、筆者所属組織(現在および過去)の公式見解を示すものではありません。
「母国語教育(政策)」は、国家主権や「国体」(國體/国家体制)護持の要諦に関わる。歴史を振り返ると、明治初期において旧・薩摩藩士で初代文部大臣・森有礼(もりありのり)公により「日本語廃止論・英語採用論」が提唱された。これは母国語また言霊(ことだま)を蔑ろ(ないがしろ)にした極論として、当時そして後世にわたって批判の的とされてきた。端的にいえば亡国の論法ということである。当節、数社の某大手企業社長がぶつ「(社内)英語公用語化論」もまた然りである。
政治学者で九州大学大学院准教授・施光恒(せ・てるひさ)氏は、その著書『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』の「第三章」で、福沢諭吉が『学問のすゝめ』の中で森有礼公を黙示(「書生」)した言を紹介している。『書生が日本の言語は不便利にして文章も演説も出来ぬゆえ、英語を使い英文を用いるなぞと、取るにも足らぬ馬鹿を言う者あり。按ずるにこの書生は日本に生れて未だ十分に日本語を用いたることなき男ならん。国の言葉は、その国に事物の繁多なる割合に従って次第に増加し、毫も不自由なき筈のものなり。何はさておき、今の日本人は今の日本語を巧みに用いて弁舌の上達せんことを勉むべきなり』 施氏はまた同著の「おわりに」で、日本の将来に対して次の様に警鐘を鳴らしている。『教育熱心な家庭では、小学生の頃から子供を海外へ留学させることが流行るだろう。日本への愛着や日本人らしい常識を持たず、日本語もうまく話せない新しい世代のエリートが日本の中枢を牛耳るようになるのはまず間違いない。』
また大手外資系企業を代表する見解として、マイクロソフト日本法人社長を務めた成毛眞(なるけまこと)氏は、その著書『』の「まえがき」で、次の様に指摘している。『英語を勉強しなければいけないという強迫観念にとらわれている人は、無批判に欧米人の考えを受け入れ、英語業界のカモの予備軍になりかけているのである。いま日本人に必要なのは、日本という母国を深く知り、自分なりの考えをしっかりと持ち、日本語でしっかりと伝えられる“日本人力”である。本当はそういう人間こそ、海外で通用するグローバルなビジネスマンなのである。』至極正論である。
さらに同時通訳者の視点として、立教大学大学院教授でもある鳥飼玖美子(とりかいくみこ)氏も、その著書『』の「終章」で大変興味深い話を述べている。『ビジネスではないが、英語を話さなくても国際的に活躍する日本人は枚挙にいとまがない。スポーツ選手もそうだし、ノーベル賞を受賞した日本人が英語を流暢に話すとは限らず、英語力とは全く別の能力や業績で評価されている。北野武氏も然りである。フランスでコマンドールを授与された際の記者会見をニュースで見ると、しっかり日本語で話している。(中略)フランス人ジャーナリストが通訳者を介して北野氏の語りを聞き取り、フランス語で書かれた原著が日本語に翻訳されている。(中略)北野武氏は英語で話す必要などないのだ。英語を話さないからといって彼の映画監督としての価値は揺るがない。日本語で思いのたけを語れば、通訳され翻訳されることで、世界にメッセージが伝わる。これが可能なのは、しかし、「たけし」が語るべき内容を持っているからだ。大事なのは、英語ができるかどうかの前に、話す内容があるかどうかである。』筆者は大いに首肯するところだ。
大東亜戦争(対米戦争)後、特に昭和後期~平成期において「言葉の乱れ」が問われて久しく、令和の現在に至っては惨憺たる状況といえる。個別に具体例を挙げるにも、余りにも多様で数も夥しい(おびただしい)ため、本稿では敢えて割愛したい。大まかに類型化すれば以下となろう。ただし所謂「若者言葉」は、他の世代では使用されず使用サイクルも短いため網羅していない。


時代を経るごとに状況は深刻化・全世代化し、一定の節目で国家(文部科学省)としての指針策定や是正が図られる必要性を感じる。筆者が「聴覚」に及ぼす強い違和感・嫌悪感の対象として、この「言葉の乱れ」すなわち「日本語の誤用(Misuse)」「外来語の濫用(Abuse)」という社会事象を捉える中、ここでは特に「外来語の濫用」の問題について順序立てて論考する。
①現代日本語の文字体系
・現代の日本語は、実に4種類もの文字で構成されている。すなわち「漢字」「平仮名(ひらがな)」「片仮名(カタカナ)」「Alphabet」である(および「アラビア数字」)。これは世界でも類がない文字体系と思われる。
・このうち「片仮名」は、主に「和製外国語」「片仮名語」で用いられている。
・また、Alphabet は、主に「略語」(Abbreviation)「頭字語」(Acronym)で用いられている。
・この文字体系(4種類の文字による言語構成)は、毎朝目を通す大手の新聞紙面でも如実に表れている。
②近代以降の外来語使用経緯
・江戸期までは、徳川幕府による鎖国体制の下、基本的に「漢字」(漢語)と「平仮名」(大和言葉)のみが用いられてきた。
・明治維新による開国以来、「脱亜入欧」政策の下、帝国列強(現在の西側民主主義国)の(外来)文字体系である Alphabet を受け入れる。
・大正、昭和、平成と時代を追うごとに、次第に日本語を構成する「漢字」と「平仮名」の割合が低下する一方、昨今急激に「片仮名」と「Alphabet」の割合が増加している様に思われる。
・「グローバル化≒米国化」を是として政治とメディアがこれを喧伝(助長)する中、「グローバル化の推進」は先進的な思想であって「日本やアジアへ拘泥(こうでい)」することは後進的であるかの様な捉え方が存在する様に思われる。
・しかし昨今の外来語を多用する風潮は、政治経済活動等の必要上や、他国文化の理解、外国語の習得など、本来の趣旨や許容度を逸脱している様に思われる。
・またこれにはファッション的な側面、すなわち外来語の使用によって、「耳障り(響き)の良い」「知的で洗練された」「先進的な印象がもたらされる」といった感覚的要素が作用している様に思われる。
・これに関連して外来語の多用が目立つものに、ビジネス用語や、企業名(創業時の由緒ある日本語社名からの変更含む)とその製品・サービス名、芸能分野(音楽・映画・スポーツ等)における Artist 名や作品名、歌詞(主要部分である Chorus、日本語を英語的に歌唱する手法含む)、ルール用語など。
・また国内企業等の広告イメージに登場する被写体(ファッションモデル)は日本人でなく外国人(主に白人)であることが多く、ここにも日本人が内包する外国人(主に白人的な「美」の基準)への根源的な羨望が窺える。
③言語学(linguistics)上の相違点
・元来、英語等の欧州系言語は「表音文字」(Phonogram)、日本語(漢字)は「表語(表意)文字」(Ideogram)である。そのためこの両者間での変換(翻訳)は、欧州系言語同士(英語とフランス語等)のそれと比較して容易ではない。このため、多くの日本人にとって英語等の原語での発音が不得手であるのは頷ける。
・また英語等の原語を日本語(片仮名)に置き換える際、日本語の音節は大部分が「母音」(Vowel)で終わるのに対し、英語等の音節では「子音」(Consonant)のみで終わるものがある。 また母音の前後に複数の「子音」が続くこともある。この部分でも、多くの日本人にとって原語での発音が不得手であるのは頷ける。
④「和製外国語」「片仮名語」「略語」「頭字語」の問題点
・「和製外国語」「片仮名語」は雨後の筍(たけのこ)の様に現れては消え、内部に閉じた関係性(日本人同士)において定着している。しかしこれらは、原語から大きくかけ離れた、適切とは言い難い表現となっているため、外部との関係性(対・母国人/Native)においては成立しない(通じない)状況となる。
・日本語に元来存在する概念であるにもかかわらず、敢えて(過度に)「和製外国語」「片仮名語」へ置き換える風潮が、大手メディアを含む社会のあらゆる領域で蔓延している。
・この背景には、(特に Negative な意味をもつ)言葉が、「和製外国語」「片仮名語」による耳障りの良い「美辞麗句」(Flowery Words)へ置き替えられることで、その「本質」が巧妙に覆い隠されている感すら覚える。
・昨今の「政治的適正性」(Political Correctness)の跋扈(ばっこ)する Sensitive な領域については、特にこの傾向が強い様に感じられる。
・Alphabet の羅列である「略語」・「頭字語」等は、さながら「記号化」「符号化」しており、その「意味」すら捉えづらく、もはや日本語(言語)としての体を成さない様に感じられる。
・このことが、日本人の英語等の習得、すなわち原語での理解、原語での発音、会話(聞く・話す)能力の上達を阻んでいる要因でもあろうと考える。
⑤総括
・高齢化が急激に進む我が国において、増加する高齢者(認知症を含む)にとって容易に理解しやすい文字体系を維持することが、今後肝要であると思われる。
・「和製外国語」「片仮名語」は、しかしながら、一定の条件下ではその使用が許容されるものと思われる。筆者が考える基準では、日本語に元来その概念が存在しないもの、また外来してから一定の年数が経過することで社会の広い世代に遍く(あまねく)浸透・定着し、日本語に準用しても違和感のなくなっているもの。
・上記に挙げた状況や問題点は、その程度の差こそあれ、日本社会における「英語等⇒日本語」の外来類型だけでなく、外国社会における「日本語⇒英語等(日本語を起源とする英語等)」の外来類型においても同様であろうと推察される。また欧州系言語において、「借用語」(Loanword)の相互使用(英語におけるフランス語やラテン語等)は一般的である。
※参考文献
施光恒 『英語化は愚民化 日本の国力が地に落ちる』、集英社、2015年
鳥飼玖美子 『』、角川書店、2010年
成毛眞 『』、祥伝社、2013年